予防診療について
- HOME
- 予防診療について
予防診療について


子犬や子猫の健やかな成長には、計画的なワクチン接種が欠かせません。
また、成長後の定期的な追加接種を行うことで感染症のリスクを減らすことができます。
さらに、寄生虫対策としても適切なタイミングでの投薬により寄生虫の感染を防ぐことが可能です。
当院では飼い主様と動物たちの暮らしに寄り添いながら、それぞれのご家庭に合わせた予防プランをご提案いたします。毎日の生活の中で実践できる健康管理の工夫も診察時に詳しくお伝えし
ますので、ぜひ一度ご相談ください。
フィラリア症について

フィラリア(犬糸状虫)は、蚊が媒介して感染する寄生虫です。
蚊が犬や猫を吸血する際に蚊の体内にいるフィラリアの子虫が犬や猫の体内に侵入し、数ヶ月で約30cmにも成長し肺動脈や心臓に寄生します。初期段階では目立った症状が見られないこともありますが、寄生虫の数が増えるにつれて血液の流れが妨げられ、咳や息切れ、運動を嫌がるなどの症状が現れます。重症化すると命を脅かす危険性が高まり、最悪の場合死に至ることもあります。
フィラリア症の治療は非常に困難でリスクが伴うため、予防が何より重要です。予防薬を正しく投与することで、感染を確実に防ぐことが可能です。大切なペットを守るために、毎年の予防を欠かさず行いましょう。
猫フィラリア症とは

フィラリア症は一般的に“犬”糸状虫症と呼ばれることが多いですが、実は猫にも感染する危険性がある病気です。猫のフィラリア症は感染に気付きにくいという特徴があります。そのため、気付いた時には病気が進行しているケースが少なくありません。
さらに、猫のフィラリア症は診断が難しい病気としても知られています。血液検査などで確定診断を下すことが難しく、症状が出る頃には命に関わる危険な状態になっていることが多いのです。
猫のフィラリア症は予防が何よりも重要です。定期的な予防薬の投与で大切な愛猫の命を守ることができます。早めの予防対策を始めましょう!
ノミマダニ予防について

【ノミについて】
ノミは犬や猫に寄生する寄生虫で、犬や猫を吸血する際にかゆみを引き起こしたり、様々な感染症を媒介したりします。何年にもわたり繰り返しノミに吸血されると、「ノミアレルギー性皮膚炎」を発症し重度に痒みに悩まされます。ノミはお散歩などで外を出歩いたときに皮膚に飛び移り寄生しますが、完全室内飼育のネコちゃんでもノミの寄生を確認した例がありますので室内飼育のペットでも注意が必要です。
寄生したノミが一度吸血をおこなうと、1日に30〜50個の卵を産むと言われています。ノミの卵は家の中に産み落とされやがてノミの成虫となりどんどん家の中でノミが繁殖していきます。そのためノミによる被害を拡大させないためにはしっかりと予防をおこなうことが重
要です。

【マダニについて】
マダニは5~10mm程度の小さな寄生虫で、吸血することにより5〜10倍ほどの大きさになります。公園や草むらなどに生息し、ワンちゃんやネコちゃんが通りがかるのをじっと待っています。主に目の周りや耳、お腹などの毛の薄い部分に寄生することが多いです。マダニは単なる痒みや皮膚炎を起こすだけでなく、「犬バベシア病」や人間にも感染する「ライム病」「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」といった重大な感染症を媒介する危険性があります。動物と飼い主様の健康を守るためにも、定期的なダニ予防を心がけ、もし寄生が見つかった場合は早めに対処することが大切です。もしマダニが寄生しているのを見つけた場合は無理に引っ張ると皮膚に噛みついているアゴ(頭部)が動物の皮膚に残ってしまい炎症が続くことがありますので、無理に取ろうとせずに病院で処置してもらうようにしましょう。
Q&A
フィラリア予防、ノミマダニ予防に関するよくあるご質問
Q1予防はいつからいつまで続ければよいですか?
A. フィラリア予防は4月から12月まで行うのがおすすめです。
ノミ・マダニ予防は1年を通して通年での予防を推奨しています。
Q2なぜフィラリア検査が必要なのですか?
A.すでにフィラリアに感染している状態で予防薬を投与すると、体内の幼虫が一度に死滅し、ショック症状を引き起こすことがあります。また、死んだ幼虫が血管に詰まると、命に関わる危険性もあります。
そのため、予防を始める前に必ず「フィラリア検査」で感染していないか確認することが大切です。
フィラリア予防を始める前には必ず「フィラリア検査」で感染の有無を確認することが重要です。
Q3どんな予防薬がありますか?
A.予防薬には、以下の3つのタイプがあります。
- おやつタイプ:おやつ感覚で与えられます。
- 錠剤タイプ:飲み薬として使用します。
- スポットオンタイプ:首筋に薬を垂らすタイプです。
Q4投与したことによる副作用はありますか?
A. 副作用はほとんどありませんが、まれに以下の症状が見られることがあります
- 飲み薬タイプ:吐き出してしまうことがあります。その場合は、もう一度飲ませてください。
- スポットオンタイプ:薬を垂らした部分がかゆくなったり赤くなることがありますが、通常は数日でおさまります。もし症状が続く場合は、当院までご相談ください。
Q5投与後何日後からシャンプーをしていいですか?
A.
- 飲み薬タイプ:投与したその日からシャンプーしても問題ありません。
- スポットオンタイプ:薬がしっかり浸透するまで2~3日後のシャンプーをおすすめしています。
予防接種(狂犬病ワクチン、混合ワクチン)について
犬には、狂犬病を予防するための狂犬病予防接種(狂犬病ワクチン)と、複数の病気を一度に防ぐことができる混合ワクチンがあります。
一方で、猫には混合ワクチンのみが使用されます。
1.狂犬病ワクチンについて
狂犬病は動物から人間に感染する非常に危険な感染症の一つです。人間が感染するとほぼ100%死亡するといわれており、さまざまな哺乳類に感染することが知られています。
現在、日本では狂犬病の発生は報告されていませんが、近隣諸国では頻繁に発生しており、日本でも感染リスクがゼロとは言えません。そのため、狂犬病予防接種を定期的に受けることが非常に重要です。
生後90日を過ぎた犬には、毎年1回の狂犬病予防接種が法律で義務付けられています。
名古屋市にお住まいの飼い主さまには、登録手続きや証票の発行を当院で代行いたします。
2.混合ワクチンについて
犬や猫の混合ワクチン接種は、伝染病を防ぐために欠かせません。
このワクチンにより動物を危険な病気から守るだけでなく、人にも感染する可能性のある病気を予防することができます。
特に、特効薬がない伝染病に対してはワクチン接種が唯一の予防策です。健康な生活を送るためには毎年の定期的な接種が重要です。動物を感染症から守るためにも計画的なワクチン接種を受けましょう。
ペットたちの健康を守る第一歩は予防から始まります。大切な家族が長く元気でいられるようワクチン接種を忘れずに行いましょう!
ワクチン接種は室内飼いの動物にも必要です
子犬や子猫の場合、初回接種は3~4週間おきに2~3回行うことが推奨されています(接種時期やワクチンの種類により異なります)。その後、成犬や成猫になった後は1年に1回の追加接種をおすすめしています。
「うちの子は完全室内飼いだから、ワクチンは必要ないですよね?」という声をいただくことがありますが注意が必要です。伝染病の中には空気感染するものがあるほか、飼い主様の靴や衣類に付着した病原体が自宅内に持ち込まれる可能性もあるのです。つまり、室内で生活しているペットでも感染リスクがゼロではありません。
ワクチンは、大切な家族の一員であるペットの健康を守るだけでなく、感染症の拡大を防ぐための重要な対策です。ワクチン接種で安心できる毎日を過ごしましょう!
| 犬のワクチンで予防できる病気 | 5種ワクチン | 6種ワクチン | 7種ワクチン |
|---|---|---|---|
| 犬ジステンバー | ◎ | ◎ | ◎ |
| 犬アデノウイルス2型感染症 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 犬伝染性肝炎 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 犬パラインフルエンザ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 犬パルボウイルス感染症 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 犬コロナウイルス感染症 | – | ◎ | – |
| 犬レプトスピラ感染症黄疸出血型 | – | – | ◎ |
| 犬レプトスピラ感染症カニコーラ型 | – | – | ◎ |
| 猫のワクチンで予防できる病気 | 3種ワクチン | 5種ワクチン |
|---|---|---|
| 猫ウイルス性鼻気管炎(猫の鼻風邪) | ◎ | ◎ |
| 猫カリシウイルス感染症(猫のインフルエンザ) | ◎ | ◎ |
| 猫汎白血球減少症 | ◎ | ◎ |
| 猫クラミジア感染症 | – | ◎ |
| 猫白血病ウィルス感染症 | – | ◎ |
当院では生活スタイルや、飼い主様のニーズに合わせた予防プランをご提案させて頂きます。他にも予防診療・ワクチン接種のことでご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
アニコム損保・アイペット損害保険に対応しています
アニコム損保・アイペット損害保険以外の保険にも対応しています。
保険ご利用の際は診察前に受付でご提示ください。

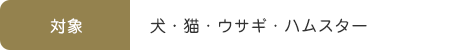
※ご来院の際はペット保険にご加入中の方は保険証も一緒にご提示ください。
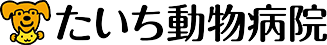


 052-896-5556
052-896-5556
